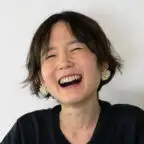清田ダイアリー KIYOTA DIARY
小吃(シャオチー)
中国語で簡単な料理を意味する「小吃」を紹介
2022年09月01日

小吃は中国語で簡単な料理とか一品料理を意味するが、この歴史は千数百年の伝統を持っている。また地方によって味が異なり、食にみる文化遺産とみる向きもある。
小吃の特徴
生産地特有の名称が付き、北京小吃、江蘇(以下小吃の文字を省略)・山東・河南・安徽・上海・広東・四川・浙江・福建・湖北・天津・東北・山西・陝西・寧夏(ネイカ)・甘粛・西海・西海・蒙族・回族ほか12族の名称が付いている。
代表例で四川小吃をみると、坦々麺・成都酸辣麺・豆腐脳ほか約100種。広東小吃は鮮肉雲呑(ワンタン)・蟹肉水餃・伊府麺ほか約50種と非常に多い。庶民の生活に密着した味と言えよう。そして咸(シェン:塩)味のメニューのみではなく甜い(甘い)小吃も含まれている。
四川の小吃で知られる冰糖銀耳は、白キクラゲを砂糖で煮た甘味で、伝統的には高級な滋養品とされ、中医学(漢方)で補腎・清肺・益胃の目的で用いられてきたとされる。

特に有名なのは北京の宮廷料理専用レストランとして知られている仿膳飯荘のメニューの豌豆黄(エンドウ豆を原料としたようかん)は、冷点心として甜口爽口・別有風味として高い評価を集めている。
同様に金糸巻・木犀糕・芸豆巻・肉末焼餅・小窩頭・棗糖糕・小包酥盒も仿膳の代表する得意の甜点心であり、何れも一口サイズで食べやすく美味絶品である。
小吃の代表例

小吃は地方の味や特産物が巧みにとり入れられており人気が高い。代表例をみると
- ・北京小吃…一品焼餅・肉餅・豆腐脳・豆汁・杏仁豆腐・八宝蓮子、蜜麻花・金糸圏・白羊頭・面茶・山薬餅、蓮子糕ほか。
- ・江蘇小吃…酥餅・蘇式月餅・五色玉蘭餅・三丁包子・蟹黄包子・五仁包子・豆沙凉巻・水蜜糕・豆腐花・三丁包子ほか。
- ・安徽小吃…小紅頭・三河米餃・紅万春水餃・小茶糕・包河藕粥・八宝緑豆汁・八公山豆腐脳・桂花糕・烤山紅
- ・河南小吃…桂花饅頭・炸油餅・千層糕・桂花饅頭・玖瑰糖糕・坦坦麺・棒棒鶏(日本で有名なバンバンジー)・豆腐脳・杏仁茶・茶湯ほか。
何れもよく知られ、美味でしかも手軽である。
- ・上海小吃…蝦肉月餅・蝦肉焼売・蟹焼売・緑豆糕・桂花糖藕・肉餡湯円・桂花糖油山芋・南翔饅頭ほか。
- ・広東小吃…鮮肉雲呑・干燒伊府麺・叉焼酥・水晶酥餃・蝦油叉燒。五仁包・鶏仔餅・蛋球・魚生粥ほかとなる。
特に広東料理は小吃としてでなく一品料理として有名なものが多くみられる。

その他各州で小吃として有名なものをあげてみると
- ・湖北…熱干麺・清水粽子、三鮮豆皮
- ・天津…十八街麻花・筋餅
- ・東北…松塔麻・油炸糕
- ・山西…仙食・拉麺・刀削麺
- ・陝西…金銭油塔
- ・甘粛…蘭州清湯牛肉麵
- ・台湾…叉焼肉粽
ほかと全中国に分派、普及をみている。
手頃で広く愛される小吃

以上にみるように小吃の歴史は長く、また全中国に普及して広く愛されている。小吃の原料となるものは米・麦・豆・きび・肉・卵・乳・粟など中国各地で容易に入手しやすいものばかりで、価格的に割高なものは全くみられない。しかも調理技法としてもよく知られている。
- ・蒸(ツェン)…蒸し物で材料を柔らかくする火を通す
- ・炸(ザ)…揚げもので油をたっぷりと使う
- ・烤(カオ)…直火焼き
- ・烙(ラオ)…小麦粉を薄焼きにする
- ・煎(ジィアン)···せんじる・いためる
- ・炒(シャオ)…油でいためる・油の量はやや多い
- ・煨(ウェイ)…とろ火でゆっくりと煮る
- ・爆(バオー)…はじける・破裂させる
- ・烩(ハイ)…あんかけにする
- ・炖(ダン)...とろ火でゆっくりと煮る
- ・冲(チュング)…水を注ぎ薄める
一般的な小吃専門店は極めて手頃で、品数も十種程度で、価格面も割安で多くの人々に人気をよんでいる。また新しい製品もみられ、江南地方の人品メニューの開口笑(かいこうしょう)などを取り扱っている店もみられる。
まとめ
中国の小吃は長い歴史を誇る中国で生まれた文化的な結晶とみられ、地方によっては全く異なり、それぞれに大差がある。A地区で生まれて人気のあるアイテムがすぐ隣のB地区やC地区に移るものではないとしている。地域に合わせた味が大切であり、経済的な実恵(安くてうまい)をポリシーとして発展を続けている。小吃の売行きは着実に上昇をみせている。要注目である。
付加価値の高い
食品・製品を開発します
清田産業では、メニュー、レシピ、調理方法、試作など、ご提案から開発までワンストップで対応します。豊富な経験と研究開発実績から、付加価値の高い製品開発を実現します。
-

全国屈指の取扱原材料
10,000種類以上 -

多角的な視点からの
課題解決 -

掛け算のアイデアと
開発力
お気軽にお問い合わせください。
この記事を書いた方

この記事を書いた方
食品評論家太木光一
1947年早稲田大学商学部卒業。同年昭和産業に入社し、一貫して調査業務に携わる。調査部長を経て1979年に退社するが、在社当時から食品と食品産業について新聞・雑誌に健筆をふるい、食品産業評論家として活躍する。通産省中小企業振興事業団の需要動向委員のほか多くの政府委員を歴任するとともに食品メーカー、問屋、高級食料・食品店の顧問にも就いていた。海外視察は280回以上に上る。主な著書は「日本の食品工業」(共著)、「新・一般食品入門」、「惣菜食品の強化技術」、「食材の基礎知識」など多数。