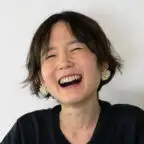清田ダイアリー KIYOTA DIARY
月餅(ゲッペイ)
中国の甜点心
2023年04月03日

数ある中国銘菓のひとつとして「月餅(ユエピン、げっぺい)があげられる。今回は月餅について詳しく紹介する。
月餅の始まり

中国では月の宮殿には「嫦娥(じょうが)」とよばれる仙女が住むと信じられており、中秋節(中秋の名月)の日に月を祭る供え物として作られた点心が、月餅の起源とされる。祭壇には月神やうさぎが描かれた絵を飾り、月餅の他に旬の果物、例えばりんごやブドウ、梨、栗などを山盛りに供える。香炉には月桂樹にみたてた生の枝豆を飾る。中秋の主祭者は女性であることも大きな特徴だ。
月を祭り終わると家族や友人が集まり、祭壇を囲み、月を眺め ながら月餅を食べる習慣から、時代の変遷とともに親しい人やお世話になった人へ節句の贈答品になっていった。
また、モンゴル民族に支配されていた元王朝の時代、天下を再び漢民族に取り戻すべく、明の太祖となった朱元璋(洪武帝)が月餅の中に「8月15日に決起する」という密書を入れ、各地の同紙に連絡を取ったとも言い伝えられ、中国の人にとって、大変思い入れのある菓子である。
月餅は味・形状・保存性の良さから全中国に広まり、広州式(広式)、蘇州式(蘇式)、北京式(京式)、雲南式(滇式)、潮汕式(潮式)など、それぞれの地域の月餅があり、各地方によって風味や見た目に特徴が見られる。
あんの種類
また中に入れるあんや皮・形状の差によって種類は非常に多くなっている。

あんのバリエーション・・・豆沙(黒小豆あん)、蓮蓉(蓮の実のあん)、五仁(五目ナッツ:胡桃、杏仁、カンランの種、ひまわりの種、ゴマ)、椰子(ココナッツあん)、百果(木の実のあん)、棗泥(ナツメのあん)、蛋蓮蓉(卵黄と蓮の実あん)、チョコレート、クリームなどの甘い月餅はもちろん、五仁あんに金華ハムを加えた金腿月餅や辛味のあるお肉を包んだミートパイのような甘くない月餅もある。
月餅の代表的な形

形状として満月をかたどった円形のものが多い。広州の有名な専門店では直径30cmに近い大月餅を作っている。一般の月餅は約7cmであるから5倍近いものである。この大月餅一個でギフトとして活躍する。本来は有名な中国料理店であるが月餅時に大盛況となる。
北京式の月餅は、角型は茅台酒入り、丸型は蓮の実・ナツメ・胡桃が入っている。また、北京北海公園内にある宮廷料理店、仿膳飯荘の仿膳仲秋月餅は大変有名であり、非常に美味であるが人気も高く手に入りにくい。

月餅は表面の模様もバラエティ豊かである。木型を使い成形するが、中身のあんの名称を彫ったものも多い。また、皮の焼き色の濃いものが豆沙の入ったもの、皮の色の淡いものは五仁が入ったものが多く、その見た目で見分けることもできる。
家庭でできる月餅の作り方 (12~15個)

材料
- 強力粉・薄力粉 各200g
- ベーキングパウダー 小さじ1/2
- シロップ 200cc
- サラダオイル(またはラード) 140cc
- 小豆あん450g
月餅の木型に打ち粉をし、あんを包んで丸めた生地は包み口を上にして型にしっかり押さえる。詰めたら台に軽く叩きつけて、型から取り出す。
月餅の中に入れるあんの種類
中のあんは小豆以外にも木の実などを使うのも美味である。ハスの実やオリーブに似たカンランの種など日本では入手困難なものもあるが、胡桃などのナッツ類やドライフルーツなどを小豆あんに混ぜても良い。豚肉やエビ餡など甘くないものを入れるのも面白い。
椰子月餅のあんの作り方
材料
- 椰子糸糖(千切りココナッツの砂糖煮)
- 白ごま
- もち粉
- ラード
- 砂糖
- 水
- 椰子糸糖(千切りココナッツの砂糖煮)を細かく切り、白ごまともち粉は軽く炒っておく。
- 鍋にラード・砂糖・水を加え、煮溶かしてもち粉を混ぜ合わせる。椰子糸糖と白ごまを加えて、よく練り合わせてあんとする。
月餅は甜点心の人気メニューのひとつ

中国菓子は、種類は多くはないものの歴史も長く奥行きの広いものであり、一般的には甜点心とよばれている。月餅は豆沙包子(あんまん)と並んで甜点心の頂点に君臨し、今後も変わらぬ人気とさらなる成長が期待できる。
付加価値の高い
食品・製品を開発します
清田産業では、メニュー、レシピ、調理方法、試作など、ご提案から開発までワンストップで対応します。豊富な経験と研究開発実績から、付加価値の高い製品開発を実現します。
-

全国屈指の取扱原材料
10,000種類以上 -

多角的な視点からの
課題解決 -

掛け算のアイデアと
開発力
お気軽にお問い合わせください。
この記事を書いた方

この記事を書いた方
食品評論家太木光一
1947年早稲田大学商学部卒業。同年昭和産業に入社し、一貫して調査業務に携わる。調査部長を経て1979年に退社するが、在社当時から食品と食品産業について新聞・雑誌に健筆をふるい、食品産業評論家として活躍する。通産省中小企業振興事業団の需要動向委員のほか多くの政府委員を歴任するとともに食品メーカー、問屋、高級食料・食品店の顧問にも就いていた。海外視察は280回以上に上る。主な著書は「日本の食品工業」(共著)、「新・一般食品入門」、「惣菜食品の強化技術」、「食材の基礎知識」など多数。