清田ダイアリー KIYOTA DIARY
トウモロコシ食の多様な世界
世界各地の食文化や食卓から見える社会の様子
2025年02月20日

世界三大穀物は、小麦・米・トウモロコシだ。そのうち最も生産量が多いのがトウモロコシだが、その割に主食としては影が薄い。しかしトウモロコシを主食とする文化圏もあって、その加工や利用のほどは小麦や米以上に奥深く感じる。私は世界各地の家庭を訪れて日常の料理を共にさせてもらっているのだが、トウモロコシ食の世界にすっかり夢中になってしまった。実は奥深いトウモロコシ粉の世界をご案内したい。
ちなみに、影が薄い理由は、トウモロコシを主食として食べる文化圏が日本から距離的・心理的に遠くて馴染みが薄いことだけでなく、トウモロコシという穀物の特性として、主食として食べるよりも家畜の飼料や工業用途や加工食品に使われる割合が多いということも大きい。
水酸化カルシウム処理で:メキシコのトルティーヤ
トウモロコシの原産地について明確にはわかっていないが、メキシコ周辺の中南米という説が有力だ。メキシコでは紀元前7千年頃には栽培の痕跡があり、数千年にもおよぶトウモロコシ食の歴史がある。
今も主食として重要な位置を占めていて、トウモロコシで作るトルティーヤは、あらゆる食事に欠かせない薄焼きパンだ。朝に家の近くのトルティーヤ屋さんに行って1キロの束で買ってきて、朝食にチョリソー入りスクランブルエッグを包んだり、夕食にチキンをのせたり。毎食食べるので1キロの束もけっこうなスピードで減っていく。

メキシコの代表的な屋台料理であるタコスも、このトルティーヤの具材をのせたものだ。実はメキシコに行くまで、日本で食べるタコスはメキシコのものと同じだと思っていたのだが、あれは主にアメリカのテキサス州生まれのテクスメクス(TEX-MEX)スタイルで、メキシコのとは別物なのだと知った。
どう違うかというと、テクスメクスのトルティーヤは小麦粉で作られたやわらかいものかトウモロコシ粉で作られたパリパリのもののどちらかなのに対し、メキシコのトルティーヤはトウモロコシ粉でできたやわらかいものだ。
家で作る場合は、トウモロコシ粉に塩とぬるま湯をまぜてこね、ひとまとまりになったらちぎってトルティーヤプレスという大きなカスタネットのような道具ではさんでつぶし、薄く平たくなったのを鉄板で焼く。
このトウモロコシ粉はマサアリナ(masa harina)と言い、トウモロコシにはグルテンがないはずなのに生地がまとまる。その秘密は、トウモロコシの粒をそのまま挽いて粉にするのではなく、水酸化カルシウム溶液で煮て皮を溶かすという処理(ニシュタマリゼーション)をしたのちに挽くという加工方法にある。
トウモロコシ粒を単純に挽いたコーンフラワーとは別物で、「コーンフラワーではトルティーヤは作れないよ」と彼らは言う。たしかにコーンフラワーにお湯を注いでもサラサラと流れるだけで一向にまとまろうとしない。ニシュタマリゼーションは、トウモロコシ粉の加工性を向上させるのだ。
ニシュタマリゼーションのさらに重要なポイントが、栄養改善のメリット。トウモロコシは必須アミノ酸のうちリジンとトリプトファンの値が低いが、ニシュタマリゼーションによってトリプトファンの吸収が良くなるのだ。これがどれだけすごいかという話は長くなるので割愛するが、リジンを多く含む豆と組み合わせることで、トウモロコシと豆だけで人間の生命維持に必要な必須アミノ酸のバランスが整うのだ。何でも食材が手に入るわけではなかった時代の尊い知恵だ。
ちなみに大航海時代にヨーロッパ人がやってきてトウモロコシを持ち帰った際、ものだけ伝わって技術が伝わらなかった結果、トウモロコシだけを食べていた貧しい農民たちの間でナイアシン不足による皮膚病(ペラグラ)が蔓延したというのは栄養学では有名な話。どうしてこんな処理を思いついたのかは想像するしかないが、古代文明の時代からトウモロコシを食してきた人たちの知恵というのは深遠だ。
一度ゆでて挽いた粉で:コロンビアのアレパ
同じ中南米でも、違ったトウモロコシ使いをする国もある。コロンビアのアレパはイングリッシュマフィンをつぶしたような形の白いトウモロコシパンだが、しっとりやわらかながら粒を感じる粗い食感で、香ばしさとやさしい甘みは老若男女に愛される味だ。日常的に家や屋台でも食べられるが、滞在先の家庭では日曜日におばあちゃんの家を訪れ一緒に作ることが毎週の行事になっていた。

アレパに使うトウモロコシ粉はマサレパ(masarepa)といって、コーンフラワーともトルティーヤのマサアリナとも別物だ。白くて粒子が粗くてざらっとしている。これはトウモロコシ粒をゆでて乾かした後に挽いて作られるもので、すでに一度加熱してあるというのが特徴だ。でんぷんがα化しているため、粉のままつまみ食いしても甘みがあっておいしく、ぬるま湯でこねるだけできれいにまとまる。
粗挽きの粉を粥状に:イタリアのポレンタ
コーンフラワーは水でこねようとしてもまとまらないと書いたが、まとまらなくても食べ方はある。アメリカ南部ではコーンブレッドにし、イタリアでは粗めのコーンミールをお粥状に練ってポレンタという名で食べる。黄色のトウモロコシを使うので出来上がりは黄金色で美しく、肉の煮込みをのせるといい汁を吸って一層おいしい。
私が一番好きなのはポレンタフリッタ(polenta fritta)という北イタリアの料理で、残り物のポレンタ粥を型で固めて直方体に切って揚げたものだ。外はカリッザクッとして、中はしっとりクリーミー。日本のイタリアレストランで見かけると必ず注文するのだが、当然レストランなので「残り物」ではなくこれのためにポレンタを作っている。いつかイタリアの家庭で本物の残り物で作ったのを食べたいと思っている。

大鍋で練り粥:ケニアのウガリ
ヨーロッパに渡ったトウモロコシはさらに旅を続け、アフリカに渡った。東アフリカを中心に広く食されているのが、ウガリなどの練り粥の類だ。ウガリはケニアでの呼称だが、各地でいろんな呼び方がされる。白トウモロコシを挽いた粉をお湯に入れて練るという蕎麦がきのような食べ物で、大鍋で作り、肉や野菜の煮込みを添えて食べる。トウモロコシでんぷんの糊化温度は65~70度なので、水やぬるま湯で練っても固まらないが、熱湯ならば固まるのだ。
最も単純な加工と調理でトウモロコシ粉を食すこの食べ方は、植民地時代に広く普及したとされる。旧宗主国であるイギリス向けに白トウモロコシを生産するようになり、そのうち現地のプランテーション労働者向けの効率的な食事として利用されるようになったのだ。そんな歴史を踏まえると、お腹に溜まることがいかに重要な利点であったかが想像できる気がする。
ケニアで滞在していた家のお母さんは「男の人は食卓にライスがあってもウガリがないと食事をした気がしないっていうんだよ」と笑いながら教えてくれた。ウガリは、ここまでに紹介したもののような香ばしさや甘みはあまりなくて、素朴で淡白な味だが、塩気の強いおかずとあわせるとちょうどいい。ケニアの中でも私が滞在していた西ケニアはナイフで切れるくらいに固くぼそぼそしていたが、海岸沿いの東ケニアの方が作ってくれたものは餅のようにやわらかく、こんなにも違うものになるのかと驚いた。

紀元前から現代までトウモロコシ加工の叡智
世界の食卓での主食としてのトウモロコシの活躍を、少し味わっていただけただろうか。ところで、マイケル・ポーラン氏によると、アメリカのスーパーに並ぶ食品のうち4分の1はトウモロコシ由来原料を含むという※。現在の加工食品界におけるトウモロコシの活躍には目を見張るが、加工食品の隆盛以前から家庭レベルで様々な工夫を凝らした加工がされてきたのだ。トウモロコシ使いの多様さに、食品工業の原点をみるようだ。
※What’s Eating America, MICHAEL POLLAN, https://michaelpollan.com/articles-archive/whats-eating-america/, 2006-06-15 (2024-11-30 最終アクセス)
付加価値の高い
食品・製品を開発します
清田産業では、メニュー、レシピ、調理方法、試作など、ご提案から開発までワンストップで対応します。豊富な経験と研究開発実績から、付加価値の高い製品開発を実現します。
-

全国屈指の取扱原材料
10,000種類以上 -

多角的な視点からの
課題解決 -

掛け算のアイデアと
開発力
お気軽にお問い合わせください。
この記事を書いた方
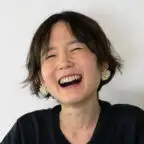
この記事を書いた方
世界の台所探検家岡根谷実里
世界各地の家庭の台所を訪れて一緒に料理をし、執筆や講演を通して料理を通して見える暮らしや社会の様子を発信している。30以上の国と地域を訪れ、170以上の家庭に滞在。京都芸術大学食文化デザインコース非常勤講師。著書に「世界の食卓から社会が見える(大和書房)」など。現在オランダ在住。
http://kitchen-explorer.com/




















