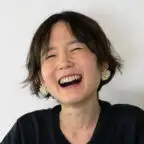清田ダイアリー KIYOTA DIARY
記憶に残る植物(2)
マメ科ダイズ(その2)
2009年03月01日

日本人の私たちは古くから大豆と付き合ってきました。その風習は私たちの体に刻まれています。今回は大豆の持つパワーを紹介します。
日本人と大豆
最近の疫学的調査研究で東洋人は欧米人に比べて、骨粗鬆症、乳ガン、前立腺ガンが少ない事実は、伝統としてダイズを多く摂食していることが理由の一つであると指摘されています。ダイズに含まれているイソフラボンには、骨粗鬆症、ガンの予防作用或いは更年期障害緩和作用、またダイズサポニンには血清脂質改善作用、脂質酸化抑制作用が認められています。
節分には豆をまき、年の数だけマメを食べる風習があります。歯の弱くなった80歳のご老人に、硬いマメを80数個食べるように勧めるのは酷ですが、どうやら深い意味がありそうです。
イソフラボンと大豆ブーム

今から10年ほど前、世界的に外因性内分泌撹乱化学物質が話題となりました。「いわゆる」のまくら言葉がついて「いわゆる環境ホルモン」と呼ばれていた時代です。ダイオキシン、PCBなどが挙げられていました。
ヒトが非意図的に作り出す化学物質が、回りまわって超微量でヒトの健康に被害を及ぼすと言われました。ヒト以外の動物、ワニにも中性化現象を引き起こし、不妊になることも指摘されていました。生殖器官に作用するため、子孫が残らなくなるという大きな問題を孕んでいます。
当時、イソフラボンも環境ホルモンに加えられ、国の研究機関でもインフラボンの健康被害について堂々とシンポジウムで発表していました。その研究発表を冷ややかな眼差しで見ている科学者がいたことも事実でした。時の流れに乗った勢いは凄まじいものです。そのことに前後して環境ホルモン学会が発足し、早速会員になりました。
現在もその学会は、より科学的な方向に路線をかえて継続していると思いますが、世間では外因性内分泌撹乱化学物質の話題は落ち着く所に落ち着いてしまいました。環境から保健へと基本的な視線が変り、健康食品について考える研究も山積した折に、脱会しました。
この時代的背景を通じて、イソフラボンにホルモン作用があることが確証された時でした。ひと呼吸する暇もなく、イソフラボンが健康維持に働くことが一斉に流れ、今日のダイズブームとなりました。
大豆タンパクとイソフラボン

栄養学的にミネラルが豊富で、必須アミノ酸のバランスも良く、ビタミン類や食物繊維多いことがダイズの特徴として記されています。それにも増して、ダイズサポニンとイソフラボンの効能が実験例に比べて、実に多い情報量として流れ、報道的に謳われています。
こんな表現も現在は流通しています。「ダイズタンパク質を与えると、血中コレステロール低下作用が認められる。ダイズタンパク質分画にはイソフラボンが濃縮されているので、このコレステロール低下作用は、イソフラボンによるもの考えられていた。」一般の方を啓蒙するには、そこそこの内容ですが、ダイズタンパク質とイソフラボンが同じ分画とは思えません。
イソフラボン配糖体とその非糖部とを区別しなければ、間違いが起きます。あくまで活性を示す化合物は非糖部です。更年期障害の女性がイソフラボンを摂取すると、顔のほてり(ホットフラッシュ)が減少する作用があります。
更年期障害に「ホルモン療法」としてエストロゲンを投与すると副作用として乳ガンの危険性が高まりますが、ダイズイソフラボンと併用することによって、その危険性を抑えます。「抗エストロゲン作用」と言われていますが、エストロゲン受容体にイソフラボンが先に結合してエストロゲンの作用を緩和するのです。

大豆に含まれるイソフラボン配糖体(ダイジン)は加水分解されてダイゼインとなり、更に腸内細菌で変換されてエクオールとなります。エクオールはダイゼインよりエストロゲニック活性が強く更年期の不定愁訴、骨密度低下、動脈硬化や肌の老化(目尻のしわ、ほうれいせん)などを緩和する作用がわかりました。
一方、外国では前立腺ガンの発生率が高く、また他の部位に転移して死亡率を高めていますが、日本人の場合、病巣が見付かるのですが、症状が出るまで進行したり、転移したりすることが少ないようです。ダイズの持つ驚くべき威力です。
イソフラボンの力

京都大学大学院家森幸男先生(現在は退職)は実際にカンポグランデ(ブラジル)、ヒロ(ハワイ)、あるいはルーイス島(イギリス)などでダイズの効能について実地調査をしました。
カンポグランデでは日系人に魚のDHAを一日3g、ワカメの食物繊維を5g(以上カプセルに入り)大豆の胚芽ふりかけ(イソフラボン50mg:豆腐100gに相当)を十週間毎日摂取してもらった。魚や海藻・大豆をほとんど食べていない日系人だから、たった三週間で効果がはっきりした。DHAを摂取したグループは血圧が下がり、ワカメを摂取したグループでは血清コレステロールが下がった。食物繊維がナトリウムを吸着したせいか、血圧も下がり、便通もよくなった。さらに、大豆のイソフラボンを毎日とった更年期の女性では、コレステロールも血圧も下がり、そのうえ骨からのカルシウムの抜けるのが抑えられた。
付加価値の高い
食品・製品を開発します
清田産業では、メニュー、レシピ、調理方法、試作など、ご提案から開発までワンストップで対応します。豊富な経験と研究開発実績から、付加価値の高い製品開発を実現します。
-

全国屈指の取扱原材料
10,000種類以上 -

多角的な視点からの
課題解決 -

掛け算のアイデアと
開発力
お気軽にお問い合わせください。
この記事を書いた方

この記事を書いた方
岐阜薬科大学名誉教授岐阜医療科学大学客員教授飯沼宗和
1947年松本市生まれ。薬学博士。1974年岐阜薬科大学大学院薬学研究科修士課程修了。1980年薬学博士取得(岐阜薬科大学)。1974年岐阜薬科大学助手、2002年教授となり、39年間にわたり専門の生薬学を中心に教育研究に携わる。1998年から4年間岐阜県に出向し、保健環境研究所所長を歴任。研究分野は民族伝承薬物の科学的根拠に基づく医薬品、健康食品、化粧品の研究開発。