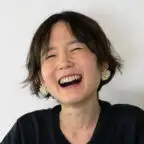清田ダイアリー KIYOTA DIARY
記憶に残る植物(7)
マメ科クズ
2009年11月01日

クズとつる性の植物について

秋の七草:ききょう(桔梗)、なでしこ(撫子)、おみなえし(女郎花)、くず(葛)、はぎ(萩)、ふじばかま(藤袴)、すすき(薄)の一つ、クズ。クズはクズカズラの略称です。葛は別に「かずら」の当て字で、つるを持つ植物の総称でもあります。従って、クズカズラは「葛葛」となります。
つる性の植物は、形態分類に従うことなく、多くの科にまたがって見られます。ビンボウ(ブドウ科)、ハカマカズラ、ヒスイカズラ、トビカズラ(以上3種ともマメ科)、ネナシカズラ(ヒルガオ科)、カギカズラ(アカネ科)、テイカカズラ(キョウチクトウ科)、ラショウモンカズラ(シソ科)、ビナンカズラ(モクレン科)などで、接頭語の意味を考えるとわくわくしそうな名前です。貧乏、袴、翡翠、飛ビ、根無シ、鍵、定家、羅生門、美男に葛が付いて植物名となります。
勿論、接尾語カズラ以外の植物にもつる性の植物は山ほどあります。フジ、エンドウ、ナタマメ、ササゲなどはマメ科で、多くの種類が見受けられます。五月の連休前後に紫に山を彩っているフジは見事ですが、絡まれた植物は至極迷惑です。
クズはフジより柔軟なつるで電柱やその支柱に絡み、滅法上に伸びていき、8月の終わりから紫色の花を付けます。もし、双方の太いつるが絡み合うと葛藤(かっとう)となります。もめごとやもつれの例えともなり頑固で解けません。
葛根湯にまつわる話

落語の枕話に『葛根湯医者』というものがあります。
「頭が痛い」、「腹が痛い」、「目が痛い」など、色々な症状を訴えるどんな患者にも葛根湯を処方して誤魔化す町医者がいました。そしてしまいには、付き添いの人にまで「まあ、いいから」と葛根湯を飲ませるものだから“葛根湯医者”と呼ばれるようになって・・・という藪医者の話です。
後半の内容は洒落ですが、前半の話は真実の部分も含まれています。
漢方には特徴的な考え方に、異病同治や同病異治があります。現代医学的には同じ病気であっても、患者の体格や条件が違うので異なった治療を行うことが漢方では一般的です。また、異なった病気でも同じ治療が行われることがあります。もろもろの証(あかし)を達観して葛根湯を処方する場合の名医としての意味合いが上記の例に含まれています。
一般的には体力がある程度ある患者の感冒の初期に多く使われたり、寒気がしたり頭痛や首筋や背筋にこわばりがある場合に用いられます。主役はカッコンで、5mm程のサイコロ状に切られた「角(かく)葛根」が使われます。
カッコンの生産方法

冬場の家内作業にカッコンの生産が始まります。子供の頃に一度根掘りを経験しました。つるの発達具合によって、根掘りの葛を定めます。太いつる程、地下の塊根が発達しています。太いつるを頼りに根堀をしますが、山の中では他の木の根が邪魔して難儀な仕事です。
横に肥大した根が伸びていて、中には直径30cmにも達するものもありますし、柔らかそうな根や繊維が発達して固そうな根もあります。その時は、水筒を準備せずに軽い気持ちで出掛けました。少し汗を流すと喉の渇きを覚えましたが、補給する水がありません。2時間余りも喉の渇きを我慢する羽目になりましたが、仕事が終わる頃には渇きが消失していました。貴重な経験でしたが、体に悪いことは子供心に体得しました。
適当な大きさに長さを揃え、家に運びます。一本一本、束子(たわし)で洗って、土を落とします。中には石を抱いている根もあります。水が切れた時点で切断に入ります。最初7mm程の輪切りにし、次いで数枚位を一緒にして、縦横それぞれ7mmに包丁を入れます。
サイコロ状に切断された根は、袋に入れ一晩水に漬け、灰汁(アク)出しします。翌朝、袋を上げますと茶色い灰汁が流れ出ます。その後乾燥ですが、冬の陽射しでは急には乾燥しません。1週間弱、乾燥して最終製品となります。

一時期、1日灰汁出した後、硫黄を燃やした中に置いたことがあります。刺激臭を出し、推奨できない方法ですが、亜硫酸ガス(二酸化イオウ)による漂白で、流石に白い根となります。水に晒すことでデンプンなどの成分が流れ出てしまうことや二酸化イオウで化学変化をおこす危険性もあり、注意が必要です。
ヤブガラシとビンボウカズラ

ビンボウカズラはヤブガラシの別名で、この植物が他の植物の上に繁って山野を枯らし、家が貧乏となるような意味だそうです。里山に人が出入りすることなく人の手が加えられなくなって、半ば自然状態に放置された今日、クズ、アレチウリ、ヤブガラシなどが繁茂してしまいました。これらはヤブガラシだけではなくビンボウカズラと言えそうです。
この秋に葛のつるを採集して成分研究を試みたり、塊根を久しぶりで掘り角葛根を作る計画を立てています。
付加価値の高い
食品・製品を開発します
清田産業では、メニュー、レシピ、調理方法、試作など、ご提案から開発までワンストップで対応します。豊富な経験と研究開発実績から、付加価値の高い製品開発を実現します。
-

全国屈指の取扱原材料
10,000種類以上 -

多角的な視点からの
課題解決 -

掛け算のアイデアと
開発力
お気軽にお問い合わせください。
この記事を書いた方

この記事を書いた方
岐阜薬科大学名誉教授岐阜医療科学大学客員教授飯沼宗和
1947年松本市生まれ。薬学博士。1974年岐阜薬科大学大学院薬学研究科修士課程修了。1980年薬学博士取得(岐阜薬科大学)。1974年岐阜薬科大学助手、2002年教授となり、39年間にわたり専門の生薬学を中心に教育研究に携わる。1998年から4年間岐阜県に出向し、保健環境研究所所長を歴任。研究分野は民族伝承薬物の科学的根拠に基づく医薬品、健康食品、化粧品の研究開発。